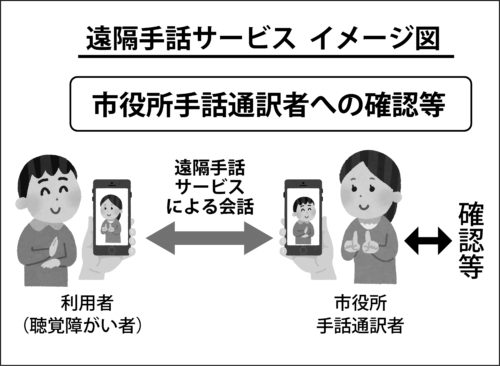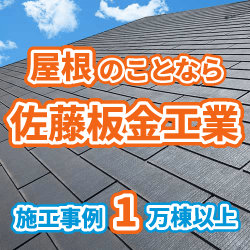新しいハウスで挑戦を広げる橋本社長
長距離ドライバーの年間時間外労働時間の上限が今年4月から960時間に制限された。いわゆる物流の「2024年問題」は今後も様々な分野に影響を与える恐れがあるが、キュウリ産地である須賀川にとって、ここにチャンスもあるという。「これまで冬春キュウリは宮崎県や九州がメインでしたが、長距離を運ぶのが難しくなると予想されます」と語るのは、ICTを活用したキュウリの試験栽培などを進める須賀川市の福島タネセンターの橋本克美社長。当地でも低コストで安定した冬春キュウリが栽培できるよう、今月から新たな試験ハウス3連棟を稼働させた。
2024年問題の懸念点が明らかになるにつれ、橋本社長のもとに冬春キュウリを卸せないか問い合わせが寄せられてきたという。
しかし当地方で冬春に栽培するには暖房が不可欠で、コストが大きな課題となる。
そこで安価に温度が保てる方法を確立し、地域に広げていくため、試験ハウスを設置した。
利用者が初期投資を抑えながらも収量を上げられるようパイプハウスの限界まで軒高を高くし、ハウス内にはヒートポンプを巡らせる。カーテンは二重にし、保温性を高めた。
将来的には地下水を使った熱交換のシステムを導入し、冬場の暖房を低コストに実現させる計画だ。「冬場でも地下水は15度程度あります。これを上手く使えば、ハウス内を栽培の適温にするためのコストが下げられます」と橋本社長。
試験のため品種や植える間隔など条件を変えながら、約1500株の栽培を試す。
水や肥料、湿度、温度等をモニターで監視しながら自動調整するシステム導入など、技術革新によりキュウリ産地を守ろうとする同社は、2024年問題を追い風にしようと国・県などの理解を得ながら取り組みを進める。
地下水の熱を野菜の栽培に活かす取り組みは、須賀川・岩瀬地域で前例がある。
天栄村湯本地区でかつて稼働していた「エコ菜ハウス」は、地熱発電の調査用に掘られた井戸の水と沢水を温度管理に活用し、冬でも低コストのレタス栽培を成功させていた。
管理団体の解散とともに施設は廃止されたが、東北大の新妻弘明名誉教授らが提案したこの「エネルギーの地産地消」の先進的な仕組みは、多くの注目を集めた。
当時、管理など担当していた星昇さんは「初期投資や井戸を掘る際の周囲の理解がクリアされ、行政のバックアップが得られれば、期待できる取り組みだ」と述べる。
かつて夏秋キュウリの収穫量で日本一を誇った須賀川に新たな活路が期待される。